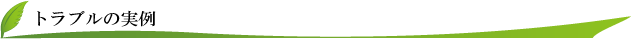
CASE-7 密葬の落とし穴
お母様本人の希望を叶える形で、家族だけで質素に無宗教の密葬を済ませたTさんと弟さん。
葬儀が終わって、お世話になった方々や親戚に無事に葬儀を終えたお知らせを送り、やっと一息ついたと思っていたら、大変なことになりました。
翌日から、ご近所や生前のお友達がひっきりなしにお香典を持って弔問に訪れるのです。
弔問に来られても、密葬だったTさんは、香典返しの品など用意していませんでした。
急いで葬儀社へ電話をしたところ、お茶のセットならあるとの事だったので持ってきてもらい、その場はことなきを得ましたが、お客様の対応でちっとも気が休まりません。
外出の予定も立てられず、家事も滞りがちになり、もうへとへと。それが毎日のように続きました。
しかし、それだけでは済まなかったのです。
次の日曜日、田舎の親戚がものすごい剣幕で怒鳴り込んできました。
「お前たちは何を考えているんだ!」
「とんでもない事をしてくれた!」
「住職に失礼な事をして!」
と怒鳴られ、「お母さん本人の希望だったのよ」と言っても聞く耳を持ちません。
一日中怒られて、後日田舎のお寺でもう一度お骨葬をするという事でやっと落ち着きました。Tさんにしてみれば、思わぬ出費の連続でした。
 トラブルの原因
トラブルの原因
Tさんの準備は完璧なように見えます。事前にしっかり下調べをして、お母様の希望通りの密葬が実現しています。
ただ一つ足りなかった事、それは「周りの方々への配慮」でした。
叔父さんや伯母さんなどの親戚とは、お母様が子供のころは一つ屋根に住む家族だったのです。
それぞれの方が特別な想いを持っているのは容易に想像がつきます。
また、友人関係でもお母様にはお母様の付き合いがあるものなのです。仲が良かった方々は、最後のお別れをしたいと思うのが普通ではないでしょうか?
この配慮を怠ったことが、混乱を招いてしまった原因です。
それから、担当の葬儀社にも問題があります。経験豊富で良心的な葬儀社さんであれば、こうしたトラブルを予測してアドバイスをしてくれるものです。
そういう事態を助言できなかった葬儀社にも責任の一端はあると言えます。
 トラブル防止策
トラブル防止策
もし身近な方が亡くなったとして、ご家族から知らせてもらえずにお別れが出来なかったら・・・。だれでもとても寂しい気持ちになりますよね?
そう頭では分かっていても、お母様の希望もある中で、両方の気持ちを立ててあげる、そんなことができるのでしょうか?
こんな場合の一つの解決策として、偲ぶ会(お別れ会)を開くことを覚えておくといいでしょう。 お葬式は密葬で済ませ、そのお知らせを「偲ぶ会の招待状」にするのです。
そうすることで、Tさんが経験したような弔問客の対応に追われることもなく、出席人数もあらかじめ把握できます。最近ではホテルでも積極的にプランを打ち出していますし、レストランでも相談に乗ってくれるところが増えています。
後日出席を取ったうえで行なう「偲ぶ会」は、本葬をするよりも安価に抑えることが可能ですし、送る側も気持ちの整理がつけられますので、精神的にも楽なことが特徴です。
もう一つ、親戚の方々の気持ちにも目を向けてみましょう。
亡くなった事実さえお知らせしないのは、今後のお付き合いもありますから、少々思慮不足だったのではないでしょうか。
そこで提案したいのは、亡くなった事をお電話でお知らせし、「母本人の強い希望で、この度は密葬ということにしますが、後日偲んでいただける席を設けますので、その時にお越しいただけますか?」と“キッパリ意向を伝えながらもお伺いをたてる”という方法です。
また、お通夜を密葬で、葬儀・告別式を一般葬で営む。こういう方法もあります。
訃報通知を告別式の日程のみにしておくことで、 通夜は身内だけでゆっくりと過ごすことができます。
 解説
解説
最近ニーズが高まっている「密葬」や「家族葬」ですが、密葬ゆえのトラブルが多発しています。その多くは、上記のような人付き合いに関するもの。
本来「密葬」というのは、対外的にお別れをする「本葬」とセットになっているものでしたが、現代は「密葬」だけが一人歩きをしている状況のため、お別れできなかった方々からのクレーム・トラブルが起きてしまうのです。
体外的な告知はせずに、身内だけで温かく見送ってあげる。それはとても良い形だと思います。今後も全国的にどんどん広がっていくでしょう。
ただ、送る側は、故人の希望や自分たちの考え方だけではなく、生前縁のあった方々が持つ「故人への気持ち」も忘れてはいけません。
また、地方によっては、「密葬・家族葬」というのはあくまでも変化球であって、必ずしも周りからは歓迎されることではないようです。
故人の生前の交友関係の広さや、社会参加の程度にもよりますが、「密葬・家族葬」を選択する場合は、「最後のお別れがしたい」と思っている方々への配慮も、今まで以上に意識する必要があります。
お葬式のニーズも、だんだんパーソナルな方向に移行しているのですが、まだまだ過渡期だということを忘れないようにしましょう。変な「しこり」が残ってしまうのは、とても悲しいことですから。
CASE-8 葬儀社の寺院手配 >>
