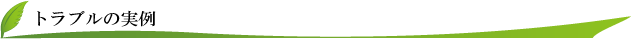
CASE-6 葬儀社の対応に怒り心頭
ある日私の手元へ届いた手紙は、
「今年父の葬儀を行ったS葬儀社のサービス内容と、請求金額に全く納得がいかないので、今回お話を聞いて頂きたくお便りしました」
という言葉で始まっていました。
時系列で便箋8枚にものぼる内容と、葬儀社の見積り、請求書が同封されていました。
内容は、最初の打合せの際の説明不足、通夜の段取りを打ち合わせる際の許せない行動、スタッフの怠慢、不透明な「サービス料」の請求など、読んでいるこちらも腹が立ってくるような内容でした。
「こういうことが実際に起きている」という実例として、葬儀社の対応の部分を抜粋してご紹介します。
今年父の葬儀を行ったS葬儀社のサービス内容と、請求金額に全く納得がいかないので、今回お話を聞いて頂きたくお便りしました。
私たちの希望としては、S葬儀社には最初から最終的な合計金額を大まかでも良いので教えてほしかったのですが、S葬儀社の説明はすべてにおいて分かりにくかったです。
見積もりも特殊な計算方法も組み込まれているようで、非常に分かりにくく、内容があちこちにちらばっていて、のちに請求書に表示されているサービス料の金額は、見積書にはのっていないのです。
私や母は父が亡くなって、しかもすぐ横に遺体がある状態なので、誰が見ても考えても、冷静な状態ではない事は分かるはずだと思います。
私と母は、頭があまり働いていない状態で返事をしていた部分がありますので後から「あの時返事をしたでしょう」といわれても困るのです。
他の親族もいたのに、冷静な第三者の意見を入れようともしないで、分かりづらい説明を続けました。
私たちは段取りも把握できず、ずっとピリピリしている状態でした。
通夜の前、式場に移動してから落ち着かない状況で司会の人が説明を始めました。それがたいそう長く、告別式のことまで一緒くたに話すので、母は「頭が混乱してあまり言葉が入らない」と少し苦しそうに言うと、司会者は「いやーまたまた!」と笑いながら言いました。
許せないのです。
そして、私たちを安心させるかのように、
「進行表をお渡ししますし、直前でも一つ一つ説明して教えます」
と言いましたが、そのようなものは一切ありませんでした。
あまりにも言うこととサービス内容が違うのです。
式場には、たくさんの女性スタッフがいましたが、2〜3人で立ち話をする姿がひんぱんに目に付きました。そうやってスタッフの方たちがあまり動いてくれなかった分、私たち親族がどれだけ埋め合わせをするように働いたか分かりません。こんな状態で「サービス料」も請求され、全然納得がいかないのです。
S葬儀社にサービス料の説明を求めると、
「よくホテルではサービス料が発生しているので、当社でも請求しています」
と言っていましたが、S葬儀社はホテル業ではないので理解できません。
もっと聞くと、「女性スタッフのサービス料」だと言いました。でもS葬儀社は広告で「女性スタッフ無料」と公表し大きく宣伝しているのです。
私はサービス料をはじめとした請求額の減額と迷惑料を希望しています。
そもそも葬式で一番大切なのは、亡くなった人間に対して遺族が感謝の気持ちをいだいて、安心した気持ちで送り出している事が絶対で、最低条件だと思うのですが、今回これを満たしていないS葬儀社には全く納得できないのです。
お手紙の抜粋は以上です。
要約すると、S葬儀社の担当者の対応・説明不足。
サービス料などに大きな不満があり、迷惑料を取りたいということでした。
大切な家族の葬儀で、ここまで気持ちを乱されるということが、どんなに残酷なことか。
請求金額の不備だけでは済まされないトラブルが実際に起きています。
 トラブルの原因
トラブルの原因
葬儀社の対応があまりにも低レベルで、ビックリしてしまいましたか?
最初にお断りいたしますが、Kさんは俗に言う「クレーマー」ではありません。
お電話でもお話しましたが、論理的にお話をする方でした。
この時は、S葬儀社の会員になっていたお母様が、会員価格ですでに依頼してしまっており、後から駆けつけたKさんとしては、他の選択肢がなかったそうです。
そこに大きな落とし穴がありました。
担当者の説明不足・能力不足はもちろんのこと、それに加えて、喪家側が「我慢」して、葬儀が終わるまで何も言わずにいたことも、怠慢を増長させた大きな原因です。
我慢せずに、分からないなら「分からないからもう一度説明してください」と、その場で言う。
スタッフの対応に疑問を持ったら、その場で「もう少し対応を考えてください」と伝え、本社や社長に直接伝える。
これが大切なのです。
 トラブル防止策
トラブル防止策
最後の精算の時になって、「まさかあの内容でこの値段?!」と我に返ったなんていうことは、残念ながら葬儀ではよくあることなのですが、我に返るのが「支払った後」では、残念ながら遅すぎます。
Kさんの希望する「迷惑料」を支払ってもらうことも難しいでしょう。
全ては「見積書にサインをしたとき」に、決まってしまっているのです。
担当者から内容の説明を受ける時、もし、「私は分からないけど、誰かが理解しているだろう」なんて思っているとしたら、かなり危険です。きっと親族の誰一人理解できていないでしょう。
まず、説明がよく分からなかったら、何度でも繰り返し聞きましょう。
次に、対応に不満があるなら、本人ではなく会社に対してすぐに苦情を言いましょう。
基準はあなた自身の感覚で結構です。
担当者の対応に「我慢」していても何にもなりません。
もしかすると、会社側は「ウチはしっかりやっている」と勘違いしているかもしれませんし、あなたが勇気を出してクレームをいうことで改善され、次に同じ思いをする人がいなくなるかもしれません。
もっと言えば、最初の見積り段階で対応に不満が出るくらいなら、たとえ時間的なロスや、探す手間がかかってしまったとしても、別の葬儀社にお願いしたほうがずっと良いと言えます。
会員価格についてはCASE-3でも解説しましたが、元のない金額を大幅値引きに見せているだけですから、何も自分から囲い込まれる事などないのです。
 解説
解説
社員がお葬式に慣れすぎて、「なあなあ」になっている。 こんな葬儀社さんは結構多いと思います。
(Kさんは、当初これで信用してしまったそうなのですが)葬祭ディレクター1級だからといって、しっかり心を込めた対応ができるということではありません。葬祭ディレクターの試験は実技ばかりで、「気持ち」や「人間性」の試験などしていませんから。
話はそれますが、あなたはどちらの人に担当してもらいたいですか?
1)経験はウン十年、お葬式なら任せとけ!とばかりに、適当に説明するベテラン担当者。
2)経験は浅くても、心を込めて親身に説明する新米担当者。
もし、1番を選んでしまったあなた、あなたはお葬式で後悔する確率がかなり高いと言えます。大切なものを見落とさないようにしてください。
「ウチは○○葬儀社でやったのよ。すごいでしょ!」などとは普通は自慢しないですよね?そう。大切なのは葬儀社よりも、担当者の質なのです。
経験や知識のない中で、お葬式の内容を決めなければならない・・・。その説明をする葬儀社の窓口が「担当者」です。担当者が説明責任を怠れば、遺族は何も分からないままどんどん進み、最後にお金だけ払うことになってしまいます。
どんなに立派な式場を持っている葬儀社でも、地域で有名な葬儀社でも、担当者が適当な仕事をしているようでは、三流葬儀社と同じことです。
その逆もしかり、式場を持っていなくても、社員が少なくても、担当者の質さえ良ければ、
一流の対応をしてもらえます。
ディレクター資格なんて、お葬式の満足度には関係ありません。お葬式が滞りなく済んでしまえば、それで表面上は丸くおさまるかもしれませんが、納得した上での依頼でなければ、気持ちの中では必ず不満が残ります。それだけ「担当者の能力」というのは、お葬式の満足度を左右するのです。
お医者さんも、治療すればそれでいいという時代ではないですよね?
治療の前にしっかりとインフォームドコンセントを行ない、患者にも分かる言葉で説明するべきですよね?
お葬式も同じなのですよ。
悲しみや不安でいっぱいの遺族に説明するのですから、上辺だけの説明では伝わりません。お身内が亡くなったというストレスで、認識力は低下しているのですから、いつもの3倍は丁寧に、誰にでも分かる言葉で説明しなければならないのです。
ご遺族の事情を一番よく分かってあげていなければならないのは、プロである葬儀社のはず。
やることだけやって、説明もひと通り流せばそれでいいということでは決してありません。
そんなことがまかり通るならば、担当者なんていらない。
説明テープでも作って、遺族が繰り返し聞いた方がよっぽどよく分かるのではないでしょうか。
そして、サービス料を10%も取るのであれば、それこそホテル並みのサービスをしたうえで、支払う方が納得するくらいのサービスをするのが、プロです。
Kさんも言っていますが、葬儀のサービスとは、送る側が安心して「ちゃんと送ってあげられた」と満足する事だと思いますし、その努力すらできない会社に、
葬儀に携わる資格があるのでしょうか。
CASE-7 密葬の落とし穴 >>
